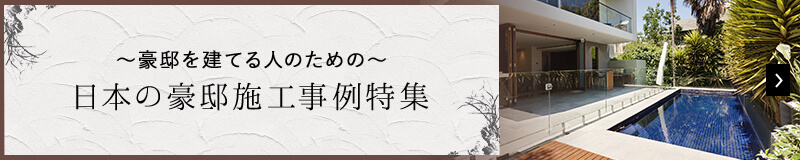道産木材とは
道産木材は、北海道で産出された木材のことです。
北海道は1年を通じて湿度や気温が低く、冬になると厳しい寒さが続きます。それにより北海道の木は時間をかけてゆっくり、しっかりと育つのが特徴です。時間をかけて育った北海道の木は木目が美しく、さらに強度も高い丈夫さが魅力。住宅や家具だけでなく、公共施設や商業施設にも道産木材が使用されています。
道産木材の魅力
品質の高さ
北海道の自然環境のなかで育った道産木材は、木材としての質の高さが評価されています。木目の美しさや堅牢な丈夫さを持つ良質な道産木材を使用することで、美しさと居心地の良さを兼ね備えた高耐久な住まいを実現可能です。
種類が豊富
道産木材は、樹種が豊富なのも魅力です。たとえば本州で使用される建築資材というとスギやヒノキ、カラマツ、ヒバなどの針葉樹が主な選択肢となります。一方で道産木材は針葉樹のほかに、ナラやクリ、ヤチダモなども建築資材として使用できるため、理想とする空間に合った木材を選べます。
輸入木材に比べて割安
コロナ前までは国産材よりも価格の安い輸入木材が多く使用されてきましたが、コロナ禍以降にアメリカで発生した住宅ブームによる建築ラッシュや人手不足などによって世界的に木材の需給バランスが大きく崩壊。輸入木材の価格が高騰したことによって、道産木材を含む国産材のほうが割安、もしくは以前ほど大きな価格差がないケースも増えてきました。
輸入木材に比べて手の届きやすい価格帯になっていることから、輸入木材の代替品として道産木材の普及が進んでいます。
環境保全に貢献
輸入木材よりも輸送距離が短いため、輸送にかかるエネルギーやCO2排出量の削減といった環境保全に間接的に貢献できるといったメリットもあります。また、道産木材を積極的に使用することで資金が森林の手入れに還元され、健全な森林環境の維持が可能に。環境に優しい住まいを実現できるのも道産木材の魅力です。
家づくりに使用される代表的な道産木材
トドマツ
トドマツは北海道に自生する針葉樹で、道内の人工林の約50%を占めるほど資源としての蓄積量が最も多い道産木材です。
材質が柔らかく加工しやすいため、北海道では建築材として一般的に使用されています。構造材から内装材まで幅広い用途に使用できるほか、木肌の主張が控えめな木材なので、幅広いテイストのインテリアと合わせやすいのも魅力。上品な白い木目を生かした使い方をされることが多く、温かみのある落ち着いた雰囲気を演出できます。
柔らかな材質で加工しやすい一方で、家具による凹み跡が残りやすい点には注意が必要です。
カラマツ
カラマツは北海道で広く植林されている針葉樹で、道内の人工林の約30%を占めます。針葉樹としては丈夫で耐久性に優れているほか、油分を多く含んでいるので水にも強く、構造材や内・外装材など幅広い用途に使用されている木材です。経年によって木肌が赤みがかった色に変わっていくのも楽しむことができます。
カラマツは節や木目の印象が全般的に強く、素朴な印象の空間に仕上がりやすいのが特徴です。上質感のあるすっきりとした印象に仕上げたい場合は、木目の印象を抑えた柾目材を使用すると良いでしょう。
硬く丈夫で耐久性に優れている一方、繊維がらせん状に育つ特性も持ち合わせており、乾燥後に割れや狂いが出やすいといった一面もあります。ただ、乾燥技術が向上したことで弱点が改善され、さらに独特の色合いが住まいに個性や美しさをもたらすとして、建材としての評価が高まっています。
道南スギ
スギはヒノキと並ぶ代表的な建築木材の1つで、北海道には道南地域に古くから植林されています。
針葉樹のなかでも軽くて柔らかく、さらに断熱性や湿度調整にも優れているため、住宅だけでなく、寺社仏閣にも使用されている木材です。住宅の建築材としては、フローリング材や壁材、天井に多く用いられています。フローリング材にスギが多く使用される理由としては、ほかの建築材に比べて熱伝導率が特に低いため。触れても肌から熱が奪われないので、冬場に素足で触れても冷たさを感じにくいといったメリットがあります。
靴を脱いで生活する日本に適しているほか、足触りが優しく、柔らかな材質で腰に負担がかかりにくいのもスギの魅力です。また、耐不朽性にも優れているため、外壁材としても重宝されています。
ミズナラ
ミズナラも北海道内に多く自生する広葉樹です。
寒さの厳しい北海道で育ったミズナラは木目が詰まっており、強度に優れているのが特徴です。柔らかい針葉樹と違って硬いミズナラは耐久性があり、傷がついたり凹んだりしにくいことから、家具やフローリングに使用する木材として人気があります。
独特の個性的な木目を持っているのも、ミズナラが建築材として人気がある理由の1つです。虎斑(とらふ)と呼ばれる虎の背中の縞模様のような木目が美しく、重厚感と存在感を放ちます。こうしたミズナラの特性や木目の美しさが評価され、かつては海外でも「ジャパニーズ・オーク」として人気を集めていました。
また、ミズナラは水分を多く含んでいるのも特徴で、曲げ加工がしやすい施工性の高さも魅力です。一方で、建材として使用する場合は、十分な乾燥作業が必要になります。
そのほかの道産木材
ヤチダモ(タモ)
道産木材として使用されるタモ材の多くが、ヤチダモと呼ばれる樹木です。高さ30m以上、幹の太さは直径1mほどの大木で、木目が美しいことでも知られています。灰白色から灰褐色をしており、落ち着いた風合いが空間になじみやすいのも魅力です。通直で均質な木目のヤチダモは家具材として古くから人気があり、バットやソリなどのスポーツ用品の材料にもなっています。
クリ
国産材のなかでもトップクラスの耐久性を持つ木材で、かつては家を建築する際は土台にクリが用いられていました。耐久性や耐水性に優れているほか防虫効果も高く、さらに木目も美しいのがクリの魅力です。一方で、その強度の高さから製材として加工がしにくく、乾燥工程も難しいことから、建材として使用されることが少なくなっています。
ハリギリ(センノキ)
センノキやセンとも呼ばれ、主に平地や山地の肥沃な土地に生息している落葉樹です。淡灰褐色で、やや粗さがあるものの、美しい木目をしています。強度や耐久性はそこまで高くないものの、柔らかく加工性に優れているのが特徴です。特性と木目の美しさを生かして、家具材や内装材、器具材などに使用されています。
エゾマツ
北海道内に自生する常緑樹で、「北海道の木」に指定されています。高さは30~40m、幹の太さが直径1m以上になることも。成木になると枝が垂れ下がって優しい印象になることから、「おんなまつ」という愛称でも親しまれています。やや黄味を帯びた色をしており、光沢があるのが特徴。比較的強度があって加工性にも優れているほか、音響性にも優れているため、建築材や家具材などのほかに、楽器材としても使用されています。
アカエゾマツ
北海道の木に指定されており、高さ40~45m、直径1.5mに達する針葉樹です。環境適応能力が高く、苗木の栽培も比較的しやすいことから、道内では主に多雪地や冷涼湿潤地で生産されています。緻密で美しい木目をしているのもアカエゾマツの特徴です。音響性能にも優れているため、ピアノの響板など楽器材としても重用されています。
シラカンバ
日当たりの良い丘陵地や山地、沼沢地に自生している落葉樹です。白い樹皮をしているのが特徴で、材は淡い黄褐色をしています。建材のほかに、工芸品や割り箸、パルプなど産業用資材としても用いられる樹木です。
道内には白い樹皮が似ているダケカンバやウダイカンバも生息しており、3種が混生していることも多いことから、「白樺」と共通の名前で呼ばれることも。また、材質も類似しているため、木材としては椛(カバ)もしくは雑椛として流通することも多いのが特徴です。
シナ
シナ(シナノキ)は、北海道・本州・九州に生育している落葉高木です。シナはアイヌ語で「縛る」を意味し、はいだ樹皮の繊維を布として織っていたことが名前の由来となっています。淡い黄褐色の色味と、均質で緻密な木目が特徴です。軽く柔らかい材質で加工しやすいため、建築用材やベニヤ材、器具材などに使用されています。
北海道の森の恵みを住まいに取り入れる
広大な総面積の約70%を森林が占め、森林資源に恵まれた環境の北海道。道産木材を使った住まいを認定する制度「HOKKAIDO WOOD HOUSE」も2025年度から開始され、道産木材を使った家づくりを推進する動きも見られています。北海道の厳しい自然の中でゆっくりと育った道産木材は、力強く美しい凛とした存在感が住まいに深みと品格をもたらしてくれます。