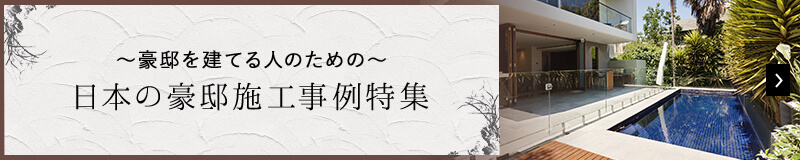リノリウムとは
リノリウムは1860年代にイギリスで開発された建材で、亜麻仁油やロジン、ジュート、松やに、天然色素などの天然素材からつくられているのが特徴です。日本では1920年からリノリウムの製造が開始され、床材として幅広く普及していました。けれど、より安価なポリ塩化ビニル製の台頭によって、リノリウムの需要はかなり低下することに。
そんなリノリウムが再び日の目を見ることになったのは、近年の環境意識や衛生意識の高まりがきっかけです。天然素材でつくられた建材としてリノリウムの安全性が見直されはじめており、さらに原料として使われる亜麻仁油が抗菌性や抗ウィルス性を持っていることから、環境や健康に優しい家づくりに関心のある人々から注目されています。
リノリウムのメリット
耐久性・耐火性に優れている
リノリウムが床材として幅広く普及していた理由は、耐久性の高さにあります。石やタイルほどの硬さはないものの、シート材に比べて頑丈で、傷やへこみがつきづらいのが特徴です。家具の重みや移動で床を傷めにくいため、長持ちしやすいというメリットがあります。
また、リノリウムは耐火性にも優れており、燃えにくいのも特徴です。火事や延焼のリスクを抑えられるため、火を扱うキッチンまわりの床にも適しています。
体や環境に優しい
リノリウムは亜麻仁油をはじめとする天然素材からできており、シックハウス症候群の原因の1つである有害な化学物質が発生しません。体に優しい素材が使用されているので、有害な化学物質による健康被害が心配な方におすすめです。また、リノリウムは土に埋めると生物によって分解されるため、廃棄時に環境を汚染する有害物質を出さないといったメリットもあります。
抗菌・脱臭効果がある
リノリウムの主な原料である亜麻仁油には、複数の菌を不活性化させる作用があり、一定の抗菌効果が認められています。病院の床材にリノリウムが使用されているのもそのためで、保育園や幼稚園、小学校などの教育施設でも採用されています。また、体力の少ない高齢者を抱える介護施設などにも適した建材です。
また、リノリウムは亜麻仁油の酸化によって酸性状態にあり、アンモニアをはじめとするアルカリ性物質を中和することができます。それによって脱臭効果も期待できるため、臭いの気になるトイレの床にもおすすめです。
お手入れがしやすい
リノリウムには汚れが染み込みにくいという特性があり、食べ物やジュースをこぼしたとしてもさっと乾拭きすればきれいになります。また、静電気がたまりにくいサラサラとした表面をしているので、ホコリや指紋がつきにくいのも特徴です。特別なお手入れやクリーニングなどは必要なく、お手入れにそれほど手間をかけなくても清潔な状態を保ちやすいといったメリットがあります。
また、ハウスダストがたまりにくいため、ご自身や家族が喘息またはアレルギー持ちという場合にもおすすめできる建材です。
転倒防止を対策できる
リノリウムには適度なクッション性と伸縮性があり、すべりにくくて歩きやすいという特性を持っています。すべりやすい洗面所やキッチンなどの水回りの床に適しており、お子さんや高齢者の転倒防止対策として有効です。弾力のある素材なので、万が一転倒した際も衝撃を吸収してくれます。
リノリウムのデメリット
独特の匂いがある
リノリウムには独特な匂いがあるため、施工後しばらくは匂いが気になる可能性があります。時間の経過によって匂いは薄れていきますが、気になる間は換気をこまめに行い、新鮮な空気を取り入れると良いでしょう。
アルカリ性や紫外線に弱い
リノリウムにはアルカリ性に弱い木粉やコルクが使用されているため、お手入れの際にアルカリ性の洗剤やワックスを使用すると、傷んだり変色したりする恐れがあります。
また、リノリウムは紫外線の影響を受けやすく、日に当たると色褪せや変色を起こす可能性がある点にも注意が必要です。日焼けした床は美観を損ねるため、日当たりの良い場所にリノリウムを使用したい場合は紫外線対策を行うようにしましょう。
コストが比較的高額
リノリウムは原料の調達や製造に手間がかかることから、一般的な床材に比べて価格が高くなります。また、リノリウムの施工には高い技術力と経験が求められるため、対応できる業者が少ないのも難点です。床材にリノリウムを使用したい場合は、施工できるかどうかを業者に確認しておきましょう。
リノリウムのお手入れ・メンテナンス方法
リノリウムは汚れがつきにくいため、日々のお手入れは掃除機掛けや乾拭きで十分です。しつこい汚れがついた際は、弱酸性~中性の洗剤を薄めて使用し、固く絞った布巾で拭き取ります。アルカリ性の洗剤や除菌剤は変色の原因になるので、使用は避けましょう。また、シミになってしまうので何かをこぼしたり、グラス跡などがついてしまったりした際は、何時間も放置せず、すぐにふき取ることも大切です。
リノリウムは耐久性の高い建材ではありますが、経年で表面がすり減ってくる場合があるため、年に1~2回程度はワックスをかけることをおすすめします。基本的に特別なお手入れは必要ないので、手間をそれほどかけなくても良好な状態を維持しやすのがリノリウムの魅力です。
リノリウムが向いている場所
キッチン
リノリウムは燃えにくいという性質を持っているため、火を扱うキッチンに適した建材です。油が飛び散ったり食材が床に落ちたりして汚れがついてしまったとしても、リノリウムならさっと拭き取るだけで済むので、手入れが楽な床材として人気を集めています。掃除のしやすさをより重視するのであれば、目地の少ないタイプのものを選ぶと良いでしょう。
また、キッチンとリビングがひと続きになっている場合は、リビングの床材との連続性や色味なども考慮して選ぶと、まとまりのある空間を演出できます。
洗面所やトイレ
リノリウムには適度なクッション性と伸縮性があり、すべりにくくて歩きやすいのが特徴です。そのため、すべりやすい洗面所やトイレといった水回りに適しています。そのほか、リノリウムはアンモニア臭の脱臭効果も実証されていることから、トイレの臭い対策としてもおすすめできる建材です。
子ども部屋
すべりにくいリノリウムは転倒防止対策に適しているほか、弾力のある素材で転倒した際の衝撃も吸収してくれるので、子ども部屋の床材としても選ばれています。色味やデザインの種類も多いため、子ども部屋らしいカラフルなデザインのものを選ぶことも可能。ただ、お子さんが成長した際に子どもっぽい部屋を嫌がる可能性もあるため、その点も考慮しながら選ぶと良いでしょう。
リノリウムとほかの床材との違い
リノリウムは環境や健康に優しい素材として再注目されていますが、主流な床材であるクッションフロアや塩ビタイルと迷っているという方もいるでしょう。マイホームに合った床材を選ぶために知っておきたい、それぞれの床材の特徴や違いについて解説します。
クッションフロアとリノリウムの違い
クッションフロアは、塩化ビニル樹脂でつくられたシート状の床材です。その名の通りにクッション性に優れているのが特徴で、耐水性が高いという利点もあります。キッチンや洗面所などの水回りに適しているほか、爪による傷もつきにくいのでペットのいるご家庭にもおすすめです。
リノリウムよりも安価で、カラーやデザインの種類が豊富なのもクッションフロアの魅力です。ビニル系素材には見えない高級感のあるデザインのものも販売されているため、豪邸の雰囲気を損ないません。一方で耐久性はリノリウムに劣り、傷つきやすく劣化しやすいといったデメリットもあります。
塩ビタイルとリノリウムの違い
塩ビタイルは、ポリ塩化ビニルでつくられたタイル状の床材です。表面が硬くて傷に強いため、もともとは商業施設や店舗の床材に多く用いられていました。その耐久性の高さが評価され、一般住宅の床材としても需要を伸ばしています。
塩ビタイルはプリントができることから、木目や大理石といった高級感のあるデザインを再現することが可能。安価かつデザインの種類が豊富なため、コストを抑えながら理想の空間を演出しやすいといった魅力があります。
ただし、塩ビタイルはタイルを1枚ずつ張り合わせながら施工するので、どうしても目地ができてしまうのが難点です。目地に汚れが溜まってしまうため、こまめなお手入れが求められます。また、足腰への負担が大きいほか、素足だとひんやりと感じるので冬場はスリッパが必要になるのも塩ビタイルのデメリットです。
リノリウムが描く上質な暮らし
天然素材からつくられたリノリウムは、健康や環境への優しさを兼ね備えた高品質な建材です。優れた耐久性や耐火性、抗菌性、手入れのしやすさなど多くのメリットがあり、キッチンや洗面所、子ども部屋など幅広い空間の床材に適しています。紫外線やアルカリ性への弱さ、コストの高さといったデメリットもあるものの、環境意識や機能性を両立できる贅沢な選択肢として注目されています。