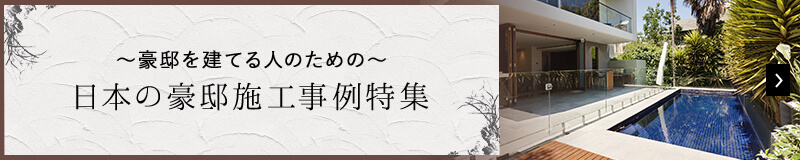無垢フローリングの魅力・メリット
無垢材にしかない自然な風合いや美しさを楽しめる
無垢フローリングは天然の木をそのまま使用するため、床材1枚ごとに木目の表情が異なる唯一無二の美しさがあります。また、経年とともに深みのある色合いに変化し、家族の歴史を刻むように味わいを増すのも無垢フローリングの魅力です。無垢材にしかない自然な風合いや美しさが、空間の質を高めてくれます。
素足で快適に過ごせる足触りの良さ
スギやパインなどの針葉樹を使った無垢フローリングは、空気を多く含んでいるので断熱性が高く、冬に素足で歩いても冷気を感じにくいといったメリットがあります。また、表面が適切な湿度に保たれているので夏のベタつく感じもなく、一年中素足で気持ちよく過ごせるのが魅力です。無垢材に含まれる空気によって踏み心地も柔らかいため、料理や皿洗いなどで立ちっぱなしになる場合でも、合板フローリング材に比べて疲れを感じにくいでしょう。
快適な湿度に整えてくれる
無垢材は調湿性に優れており、湿度が高いときは湿気を取り込み、乾燥しているときは湿気を放出して快適な室内環境に整えてくれます。湿度の変化を抑えたい場合は、室内の広範囲に無垢フローリングを採用すると良いでしょう。また、柔らかい樹種のほうが調湿性に優れているため、快適な室内環境を維持したい場合はスギやヒノキなどの針葉樹の無垢フローリングを選ぶのがおすすめです。
化学物質が使われていない
合板フローリングに使用される接着剤には、シックハウス症候群の原因となる物質が含まれています。一方で無垢フローリングは自然の木をそのまま使用しているので、化学物質が含まれていません。小さいお子さんやアレルギー体質の方でも安心して過ごせるため、家族にやさしい住まいを実現できます。
無垢フローリングの注意点・デメリット
価格が高い
無垢フローリングは一般的な合板フローリングと違って大量生産が難しく、1枚あたりの単価が高くなる傾向にあります。特に希少性の高い樹種は市場に出回る量が少ないため、割高になりがちです。
とくに、希少な輸入木材を原料とした無垢フローリングは、世界情勢の影響を受けて価格が高騰することも。流通量も安定していないので、納期遅延が発生する場合もあり、工期が長引く可能性もある点に注意が必要です。
また、フローリングは床面積分の木材が必要になるため、予算を考慮しながら適した樹種を選ぶ必要があります。
割れや変形のリスクがある
無垢フローリングは水分によって膨張・伸縮するので、木割れや反りなどが発生する場合があります。割れや反りなどを軽減するには、これらのリスクを見据えた施工が可能な会社を選ぶことが重要です。誰が施工しても一定の品質を確保できる合板フローリングと違い、会社選びを慎重に行う必要があるのも無垢フローリングのデメリットと言えるでしょう。
傷や汚れがつきやすい
無垢フローリングは空気の層を多く含んでおり、さらに表面加工もされていないので、傷や凹みがつきやすいといったデメリットがあります。また、汚れが染み込みやすく、食事や飲み物をこぼした際もすぐに拭かないとシミになりやすいので注意が必要です。硬い樹種の広葉樹であれば傷は付きにくいものの、踏み心地は硬くなります。そのため、使い心地とのバランスを考慮して選ぶことが大切です。
ただ、硬い樹種・柔らかい樹種のどちらも、浅い傷であれば研磨で補修が可能です。
無垢材の針葉樹と広葉樹の違い
無垢材に使用される原木には針葉樹と広葉樹があり、それぞれで特徴が異なります。外観や機能性も変わってくるため、自邸に合った床材を選べるように、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
針葉樹の特徴
葉が針のように細長くとがっており、上へとまっすぐに伸びていく樹形をした樹種です。木材としては材質が軽くて柔らかく、加工しやすいといった特徴があります。また、肌触りが良く、衝撃吸収性や調湿効果を兼ね備えているのも、素足で生活することの多い日本では大きなメリットと言えるでしょう。床材に使用される代表的な針葉樹としては、スギやヒノキ、パイン(松)などがあげられます。
柔らかくて肌触りが良い一方で、傷がつきやすいといったデメリットも。ただ、傷も味わいと感じられる風合いがあるのも針葉樹の魅力です。
広葉樹の特徴
丸い葉先をしており、横方向に枝が大きく茂っていく樹形をした樹種です。無垢フローリングに使用される代表的な広葉樹には、オーク(ナラ)やアカシア、メイプル、ウォールナット、チーク、カバ(バーチ)などがあげられます。
針葉樹に比べて育成に時間のかかる樹種が多く、一度に入手できる量が少ないため、針葉樹に比べて価格は高め。一方で、広葉樹は硬い樹種が多いので、傷や凹みがつきにくい耐久性の高さが魅力です。小さなお子さんやペットのいる家、人の出入りの多い部屋など傷のつきやすい部屋の床材に適しています。
はっきりとした木目の広葉樹は硬質な雰囲気があるため、無垢フローリングにあたたかみのある印象を求める人だと、理想のイメージとは異なるかもしれません。
代表的な無垢フローリングの樹種
スギ(杉)
日本にしか生息していないスギは日本人にとって最も身近な木で、建築材としてもかなりポピュラーな樹種です。足触りが柔らかくすべすべとした質感をしており、弾力性にも優れているため、踏み心地や肌なじみの良さも魅力。空気を多く含んでいるので、断熱・蓄熱性が高く、冷たさを感じにくいのも床材としての大きなメリットと言えるでしょう。
一方で、傷がつきやすく汚れやすいといったデメリットもあります。ただ、傷や汚れは使っていくうちになじんでいき、補修で目立ちにくくさせることも可能です。
新しい無垢板はスギの木の香りが強いため、森林浴をしているような気分を味わえます。
ヒノキ(檜・桧)
日本を代表する高級木材で、柔らかな木肌とリラックス効果のある爽やかな香りが特徴です。ヒノキ特有の香りには、抗菌・防虫・消臭効果が期待できる成分も含まれています。
スギと同様に柔らかな踏み心地をしているため、床材に適している樹種の1つです。無垢材のなかでも耐久性が特に高く、法隆寺や東大寺など歴史的建築物にも用いられています。また、浴槽にも使用されるほど水に強いのも特徴です。
耐久性が高いヒノキですが、表面は柔らかいため、傷や摩耗にはある程度注意が必要です。構造材としては非常に優れていますが、床材としては慎重な扱いが求められます。
パイン(松)
代表的な針葉樹の1つで、世界中で使用されています。さまざまな産地のものがあり、流通量が多いのは欧州産のレッドパインです。国産のパイン材としては、アカマツやクロマツ、カラマツなどがあげられます。
パインは無垢フローリング材として人気が高く、素朴で温かみのある雰囲気が魅力。価格も比較的手頃で、導入しやすい床材のひとつです。全体的に白っぽい色合いをしていますが、時間の経過によって茶系の色味に変化し、味わいが増すのもパインの特徴です。
オーク(ナラ)
どんぐりの木としても知られる樹種で、強度や耐久性に優れているのが特徴です。弾力性にはやや欠けるものの、硬さがあって傷や凹みがつきにくいことから、靴を履いて出入りする店舗の床板に採用されることもあります。床材以外にも高級な家具や船、ウィスキーやワインの樽など幅広い用途で使用されている樹種です。力強くはっきりとした木目をしており、虎斑(とらふ)と呼ばれる虎の斑紋のような木目が所々に現れることでも知られています。
ウォールナット
くるみの実がなる木で、無垢材としては世界三大銘木の1つである「ブラックウォールナット」が有名。黒~茶褐色の落ち着いた色合いをしており、重厚感のある美しい木目をした樹種です。使い込んでいくうちに色が抜けて明るい色合いに変化し、木目も温かみを増していくのが特徴。耐久性に優れているので傷がつきにくく、湿気や乾燥による膨張・収縮といった変化も起こりにくいといったメリットがあります。
高級家具材としても世界的に人気があり、豪邸の品格をより高めてくれる樹種と言えるでしょう。
チーク
ブラックウォールナットやマホガニーと並ぶ世界三大銘木の1つ。東南アジアを中心に亜熱帯の気候で育ったチークは、硬く強靭な耐久性の高さが特徴。天然の油分を多く含んでおり、水気に強く、防虫性にも優れているといった強みを兼ね備えています。茶褐色の風合いは高級感があり、耐久性の高さと見た目の美しさで床材として人気のある樹種です。高級リゾートホテルやブランドショップなどの内装材にも採用されています。
アカシア
ベトナムやマレーシアなど東南アジアを中心に亜熱帯地域で生育する樹種です。数百種類の品種が存在すると言われており、日本で流通しているアカシア材の多くは東アジア原産のものとなります。アカシア材は、赤~茶褐色の不均一な色味をしているのが特徴です。アカシア特有の色のコントラストを楽しめるのが魅力で、適度な硬さと加工性の良さから、床材としても人気を集めています。
カバ(バーチ)
カバは、中国やロシア、ヨーロッパに広く分布している広葉樹です。日本でも北海道などに自生しており、産地によって木肌の色が異なります。たとえば北海道やロシアなどの寒冷地で育ったカバの木肌は白く、中国西南地方のカバはピンクの色味をしているのが特徴です。いずれも柔らかで主張しすぎない色合いをしており、優しく上品な印象に仕上がるのが魅力。滑らかな木肌と割れにくく加工しやすいことから、フローリングに適している樹種です。
ブラックチェリー
アメリカ北東部が主な原産地の広葉樹で、高級木材としても知られています。赤褐の色味をしており、経年変化によって色合いに深みが増すのが特徴。濃淡のはっきりした表情を楽しめるのもブラックチェリーの魅力です。木材に含まれる油分が自然なツヤ感を生み出し、ブラックチェリーの深い色味を際立たせます。ささくれや毛羽立ちがしにくい滑らかな木肌をしており、無垢フローリングとしても人気がある樹種です。
チェスナット(栗)
チェスナットは耐久性や強度に優れており、神社仏閣の土台や鉄道の枕木としても利用されている樹種です。ポリフェノールの一種であるタンニンを多く含んでおり、経年により落ち着いた黄色味を帯びていき、味わい深い雰囲気を楽しめるのも特徴です。また、タンニンにはカビや虫などを防ぐ効果もあると言われています。
重厚で力強い木目をしており、着色の塗装のりも良いため、はっきりとした美しい木目を生かしたアンティーク調のフローリング加工も楽しめます。硬さもしっかりあるので、床材に適した樹種です。
ハードメープル(楓)
北米を代表する広葉樹で、メープルシロップの原料が取れる木として知られています。白の女王とも評される白く滑らかな木肌と美しい木目をしており、意匠性の高さと加工のしやすさから、世界的に人気のある樹種です。
床材や家具、高級車の装飾品などに使用されているほか、硬く衝撃に強い材質を生かして、ボーリングのレーンやピンにも使われています。原産地の北米では伐採が規制されているため、流通量は多くありません。無垢フローリング材としての流通も少ないので、入手が困難になる可能性があります。
無垢フローリングのお手入れ
掃除機やほうきをかけて乾拭きする
日常的なお手入れとしては、一般的なフローリングと同様に掃除機やほうき、ドライタイプのフローリング用掃除シートを使って表面のほこりや髪の毛を取り除きます。ただし、柔らかい樹種の無垢フローリングは傷や凹みがつきやすいので、床に強くあてず、優しく汚れを取り除きましょう。
掃除機やほうきなどを使って汚れを取り除いた後は、汚れがまだ気になる場所を木目に沿ってさっと乾拭きします。無垢フローリングは水分を吸い込みやすいので、日常的なお手入れで濡れた雑巾やウェットタイプのフローリング用掃除シートなどを使用するのは避けましょう。ただし、食べ物やジュースをこぼしてしまった、汚れが目立つなどの強い汚れは固く絞った雑巾で拭き取ってください。
板の隙間の汚れも掃除する
板と板の隙間にたまったゴミや汚れを放置すると固まってしまうので、つまようじなどで隙間の汚れを時々かき出し、掃除機で吸いましょう。湿気の多い日は無垢材が膨張して隙間がなくなるので、乾燥による収縮で隙間が広がる湿度の低い日や冬場に掃除するのがおすすめです。
ワックスを年に1~2回塗る
無垢フローリングの施工直後に塗布されたワックスは、日常の使用や拭き掃除などで塗料が少しずつ減ってしまいます。メンテナンスとして年に1~2回の頻度でワックスを塗り直すと、汚れの防止効果が高まるほか、表面にツヤも出て見た目も良くなります。ワックスを塗らなかったとしても、フローリングがすぐにダメになるわけではありません。ただ、快適な状態を保つためにも、年に1〜2回の定期的なワックス塗布をおすすめします。
ただし、頻繁にワックスを塗り直したり、多量のワックスを塗布したりするのは、ベタつきや黒ずみの原因になるので注意が必要です。
水や醤油などをこぼした場合
水や飲み物をこぼした場合は、固く絞った布巾や雑巾ですぐに拭き取るようにしましょう。すぐに拭き取ればワックスの撥水作用によって過度な浸透を防げるため、シミになるのを回避できます。
また、醤油やソース、ケチャップなどをこぼした場合も、できるだけすぐに拭き取ってください。油っぽいものをこぼしてしまったときは、中性洗剤(食器用の洗剤も可)を固く絞った布巾や雑巾にうすく染み込ませて拭くと、洗剤の成分によって油分が浮きやすくなり、汚れが落ちやすくなります。
酸性やアルカリ性の洗剤・溶液は、無垢材が傷んだりシミになったりしやすいので、使用は避けてください。
子どもが油性ペンで落書きした場合
目を離している隙に子どもが油性ペンで床に落書きをしてしまった場合は、サンドペーパーで表面を削れば落書きを消すことができます。汚れの染み込みが浅い場合は、消しゴムで落ちることも。落書きを落とした後は木くずや消しゴムのカスを掃除機で吸い、雑巾でさっと乾拭きして、掃除した部分のワックスを塗り直しましょう。
足元から生まれる住まいの風格
無垢フローリングは合板にはない本物ならではの質感があり、家族の歴史とともに深みを増す経年美が豪邸にふさわしい風格をもたらしてくれます。唯一無二の木目や上質な肌触り、香りは豪邸で過ごす日々の暮らしをより豊かで格別なものにしてくれるでしょう。足元にまでこだわる贅沢は、住み手の美意識や品位を静かに語ります。