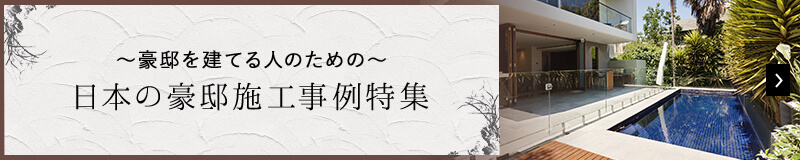3階建てのメリット
眺望や採光に優れている
3階建てのメリットは、その高さを活かした「眺望の良さ」にあります。国土交通省によると、一般的な2階建ての高さが平均7mなのに対し、3階建ての標準的な高さは12.9mです。高い建物が周囲にない環境であれば、満足度の高い眺望を楽しむことができるでしょう。さらに、屋上をルーフバルコニーとして活用することで、より高い位置からの眺望や開放的な時間を楽しめるのも3階建ての魅力です。
また、吹き抜けや天窓を設置すれば、光や風をたくさん取り込め、明るく快適な空間を実現できます。
フロアが増えて空間に余裕が生まれる
2階建てよりもスペースに余裕があるため、家族構成に応じて必要な部屋数を確保できるのも3階建てのメリットです。さらに、ビルトインガレージやシアタールームといった趣味の空間や、大容量の収納スペースなど、こだわりを反映した空間づくりを楽しめます。
また、各フロアを目的別に使い分けられるのも魅力です。たとえば、1階部分を店舗や事務所として利用したり、子どもが独立した後に使わなくなったフロアを賃貸に転用したりといった活用も可能。さらに、2世帯住宅として設計するなど活用の幅が広いので、家族構成やライフスタイルの変化にも柔軟に対応しやすいといったメリットがあります。
象徴的な外観デザインが可能
高さを活かせる3階建ては、邸宅としての存在感や個性を際立たせやすい点も魅力です。大きなファサードや重厚感のある外観デザインは、住宅そのものをシンボルとして際立たせ、街並みに映えるランドマーク的な存在となります。
平屋や2階建てでは出せないボリューム感と立体的な造形は、デザイン性を重視する方にとって大きな魅力。高級感を演出しつつ、唯一無二の邸宅として誇れる外観を実現できます。
防犯性が高い
3階建ての家は、住空間を2階や3階に配置できるため、防犯面でも安心感があります。寝室やプライベートなスペースを高層フロアに設ければ、外部からの侵入リスクを低減できるのが大きなポイント。さらに、視線が届きにくい高さを確保することで、外部から生活空間を覗かれる心配も少なくなります。
豪邸や邸宅を検討する方にとって「資産や家族を守る」という観点は欠かせないもの。防犯性を高めつつ、安心して暮らせるのは3階建てならではのメリットです。
水害に備えた暮らしを実現できる
メインとなる住空間を2階・3階部分に割り当て、1階をガレージなどにすることで、台風や豪雨で床上浸水が起きても住空間への被害を軽減できます。気候変動によってゲリラ豪雨の発生回数が増えているため、水害リスクに備えることが大切です。
家を建てる際は、近隣に河川がないか、ハザードマップで浸水地域に指定されていないかを確認しましょう。こうした土地に家を建てる場合は、水害対策を十分に検討することが欠かせません。
3階建てのデメリット・後悔しやすいポイント
1階と3階で温度差が生じる
3階建てはフロアが縦に重なっているため、上下階で温度差が生じやすい点に注意が必要です。
上下階で温度差が生じる原因は、空気は暖められると上へ流れ、冷たい空気は下に溜まるためです。その結果、全体の温度を一定に保つのが難しく、最上階の3階は夏に室温が上昇して暑くなりやすく、1階部分は冬に寒くなりやすいというデメリットがあります。
温度差を解消して快適な室温を保つには、断熱性・気密性の高い仕様を選ぶのが基本です。また、全室空調の導入や天井へのシーリングファンの設置などで空気を循環させれば、1階から3階まで建物全体に心地よい温度の空気を行き渡らせることが可能。3階建てで快適な暮らしを実現するには、温度差への対策が欠かせません。
工期が長く、コストも高くなりやすい
平屋や2階建てと比べると、3階建てはコストが高くなる傾向があります。工期が長くなりやすく、人件費がかさむほか、建て替えの場合は仮住まいにかかる費用負担も大きくなります。工期の長さは家づくり全体の費用に大きく影響するため、費用を抑えたい場合はハウスメーカーや工務店と相談し、工期の短い構造や工法を検討すると良いでしょう。
また、3階建ての家を建てるには構造計算が義務付けられており、さらに地盤沈下リスクに備えるための地盤調査も行う必要があります。構造計算や地盤調査を依頼するのにも費用がかかり、さらに地盤の改良が必要と判断された場合は大きな出費につながる点に注意が必要です。
家を建てるうえでの制限が多い
ほとんどの土地は都市計画法で用途地域が指定されており、決まった条件の範囲内で設計しなければなりません。
たとえば、防火・準防火地域に木造の3階建てを建てる場合は、外壁を耐火仕様にする必要があります。そのほか、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域に指定されている場合は、日陰規制や北側斜線制限の対象となります。
これらの条件によって建物や屋根の形が制限されることがあるため、建てる予定の土地にどのような制限がかかるのかを把握しておきましょう。
メンテナンス費用が高い
建築コストのほかにも注意すべきなのが、メンテナンス費用の高さです。たとえば外壁の塗り替えを行う場合、2階建てに比べて塗装面積が広くなる分、材料費が高くなります。さらに足場の設置費用や作業費用も増えるため、トータルコストが割高になりやすいです。
外壁のメンテナンス費用を少しでも抑えるには、防汚性や耐久性の高い外壁材を選ぶようにしましょう。
また、屋根のメンテナンスにも注意しましょう。屋根材や防水シートの寿命が短いと補修の頻度が増し、さらに太陽光パネルを設置している場合は一度撤去が必要になるため、その分の費用もかかります。長期的な負担を軽減するには、屋根材や防水シートも耐久性の高いものを選ぶことが重要です。
建物が揺れやすい
建物は階層が増えると、揺れの影響を大きく受けやすくなります。揺れといえば地震を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、それだけでなく近くを走るトラックや電車による振動、風の影響など、日々さまざまな揺れを受けています。揺れによる負担が蓄積すると、外壁や屋根に亀裂が生じたり、倒壊につながったりする恐れがあるため注意しましょう。
将来的に都市直下型の地震も起きると想定されているため、揺れの影響を受けやすい3階建ては耐震性を高める対策が欠かせません。
揺れへの対策としては、耐震性に優れたSE構法や免震工法などを検討すると良いでしょう。
階段の上り下りが大変
3階建ての家は階段が増えるため、上下階を移動する負担が大きくなります。移動の負担だけでなく、足腰が弱くなる高齢者や小さい子どもは階段を踏み外して転倒するリスクもあるため注意が必要です。二世帯住宅を検討している、あるいは将来年齢を重ねても快適に暮らしたい場合は、親世帯の生活スペースや主寝室を1階に配置するなど間取りを工夫しましょう。
設計段階から将来的な移動負担を考慮し、工務店やハウスメーカーと相談しながら間取りを検討するのがおすすめです。あるいは、ホームエレベーターを導入するのも上下階の移動負担の軽減につながります。ホームエレベーターがあれば、家具や家電を上階に搬入するのも容易になります。
Wi-Fiの電波が届きづらい
Wi-Fiの電波は上下方向に届きにくいとされており、階層の多い3階建てではつながりにくくなる可能性があります。インターネットが生活の基盤となっている方も多いため、Wi-Fiが不安定だと仕事や生活に不便を感じるでしょう。
3階でも快適にインターネットを利用するには、2階に回線を引く、中継器を設置してWi-Fiエリアを広げるなどの対策が必要です。
家を売却しづらい
3階建ての家は「階段の上り下りの負担」「メンテナンス費用の高さ」「耐震性への不安」などの理由から、売却時に買い手が見つかりにくいという課題があります。もしもの売却に備えるのであれば、エレベーターや昇降機を設置する、耐震診断を受けるなど、買い手の不安を和らげる工夫を取り入れることが大切です。
平屋や2階建てでは届かない、その先にある上質な暮らし
3階建ての家は、空間にゆとりを生み、洗練された暮らしを実現できるのが大きな魅力です。眺望や趣味のための専用スペースなど贅沢な設計が可能な一方で、建築費やメンテナンス費用は高額になりがちです。だからこそ、耐久性の高い素材を選び、将来を見据えた間取りや設備投資を検討することが、快適さと資産価値の両立につながります。
さまざまなデメリットはあるものの、平屋や2階建てでは味わえない開放感やステータス性は、3階建てならではの特権。こだわりを反映した設計は、暮らしに快適さと多様性をもたらしてくれるでしょう。