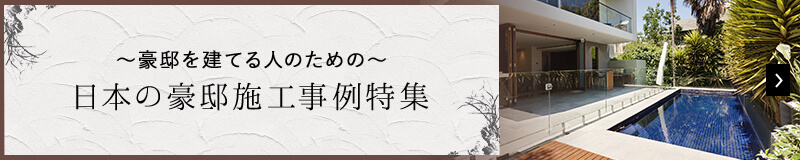チークとは

チークはシソ科チーク属の落葉性高木を総称する名称であり、木材としては世界三大銘木の一つとして世界中で根強い人気を誇っています。
チークの特徴はきめ細やかな木目の美しさと鮮やかな色味であり、家具やフローリングなどの素材として活用した際には見事な仕上がりを叶えられることがポイントです。
そのため高級木材として幅広い人気を誇っており、また雨季と乾季のあるエリアで育つチークは耐水性や防腐性にも優れていることから、クイーンエリザベス2号やタイタニック号、オリエント急行といった世界的に有名な乗り物にも採用されています。
一方、人気の高まりに比例して伐採が進められたチークは数が減少しており、現在はワシントン条約の保護対象に登録され、市場での入手が極めて困難になっていることもポイントです。
チークの魅力
きめ細やかな木目の美しさ
チークの魅力として、きめ細やかで美しい木目を見逃すことはできません。
優しく明るい色味は華やかな家具や絢爛な空間の雰囲気づくりにも適しており、古くから高級家具や調度品の素材、豪邸や豪華客船の内装などに利用されてきました。
上品で美しいチークはさまざまな場面で利用できるため、さまざまなコンセプトやテーマに合わせて活用できることも魅力です。
時の流れで変わる魅力と変わらない魅力
チークの表面は空気に触れて少しずつ色合いを変化させていき、時間の流れによってその微妙な味わいの移り変わりを楽しめます。
一方、チークは経年劣化しにくい素材としても知られており、時間が経っても変形や歪みが生じにくいことも見逃せません。
アンティーク家具や調度品の素材として経年変化による楽しみを感じながら、長い年月を経ても劣化することなく品質を保てる安心感と安定性の両立は、まさにチークならではの魅力です。
狂いが少なく虫害にも強い
チークは狂いが少なく、素材として加工しやすいことが魅力です。また、チークは虫害にも強いとされており、大切な家具が害虫によって傷つけられて品質が低下するリスクがあまりありません。
そのため、本物のチークを使ったアンティーク家具は現在でも市場で高値で取引されています。自分の世代だけでなく子供や孫の世代へと受け継いでいけることは大きな楽しみでもあるでしょう。
耐水性や耐久性に優れており腐りにくい
チークは雨季と乾季がある高温多湿なエリアで長い時間をかけて成長する樹木であり、その優れた耐水性や耐久性によって古くから造船に活用されてきました。そのため、チークは国際的に知名度の高い豪華客船などにも利用されており、愛好家からは憧れの的とされています。
カビが生えたり腐ったりといった劣化にも強いため、湿気が多くて温度変化の激しい日本においても、チークは豪邸に取り入れる木材として相応しい魅力と特性を備えています。
気軽に取引できない特別で希少な木材
チークはワシントン条約で保護されるなど、極めて希少性が高く入手困難な木材です。そもそもチークの木は成長が遅く、苗木から成樹になるまでに1世紀の時間が必要なことも珍しくありません。高級木材として需要が高まったチークは、成長速度よりも伐採速度の方が遙かに速く、結果として現在では気軽に取引できない希少素材となりました。
チークの歴史
世界三大銘木の中でも、高級なインテリアや建造物の内装材として扱われてきた歴史に関しては、チークが最も古いと言えるでしょう。
チークは、ローマ帝国の頃にはすでに宮殿や寺院の建造に使用されていたとされ、原産国の東南アジアとヨーロッパを紀元前からつなぐ架け橋の1つになっていたことが重要です。
また、現代的に高級素材として注目されたのは18世紀頃、ヨーロッパでウォールナットやマホガニーの伐採が進んで市場での供給量が減少した際、イギリスの植民地であった東南アジアからヨーロッパへ再びチークが輸入されるようになりました。
その後、20世紀頃までにチークは世界三大銘木の一つに並び称されるほどの地位を築き上げましたが、一方で過度な伐採で数が減り、現在は保護対象に指定されています。
チークの種類
2千年も前から木材として存在しているとされるチークですが、現在の日本で流通しているチーク材は主にミャンマー産のチークとインドネシア産のチークです。
以下にそれぞれのチークの特徴をまとめました。
ミャンマーチーク(本チーク)
ミャンマーはかつて「ビルマ」と呼ばれ、1948年に独立するまではイギリスの植民地として支配されていた歴史があります。その植民地時代にチークが高級木材としてヨーロッパで広まったことから、ミャンマーを原産地とするミャンマーチークは「本チーク」とも呼ばれ、現在でも高級木材として認知されています。
一方、ミャンマーチークは1948年の独立から1988年まで政府の鎖国政策によって輸出が停止され、さらに伐採から出荷まで6~7年もかかるという特性があり、国際的なマーケットでほとんど入手できませんでした。
現在は2011年の軍事政権の解散により、良質なミャンマーチークの輸出が再開しています。
インドネシアチーク
ミャンマーチークの取引ができなかった時代、チークといえばインドネシアを産地とするインドネシアチークが一般的でした。
ミャンマーチークと比較してやや色合いが薄く、インドネシアチークは伐採の時期や出荷までの時間が早いため、全体的にサイズが小さいという特徴があります。
しかし、その分ミャンマーチークよりも安価で取引されており、安定的な供給が期待できることが強みです。若木特有の明るく爽やかな色や雰囲気がインドネシアチークの魅力であり、経年変化による差を味わいたい人にとってはミャンマーチークとの比較も楽しみの要素かもしれません。
チーク以外の世界三大銘木
ウォールナット

ウォールナットは古くからヨーロッパなどで王侯貴族に愛されてきた高級木材であり、深い焦げ茶色の色合いは落ち着きと温かみを備えた品格のある佇まいを演出します。一般的には北米原産のアメリカンブラックウォールナットが「ウォールナット」として扱われますが、その他にも産地によってさまざまな種類があり、複数の品種を接ぎ木によって掛け合わせて作られたウォールナットも存在します。
マホガニー

マホガニーは、ヨーロッパでウォールナットの人気が高まり供給量が追いつかなくなった18世紀頃に、ウォールナットの代わりに高級木材として扱われるようになった木材です。美しい木目は「リボン杢」と呼ばれ、見る角度や光の当たり方で輝いて見えることからさまざまな分野で利用されてきました。
しかしその人気の高まりによって違法伐採も相次ぎ、現在はワシントン条約などで輸出入が厳しく規制されています。